炎のあるくらし
「薪ストーブを
生活に取り入れるためには」
|
|
-
|
 |
Encore
バーモント キャスティングス
|
-
|
聞き手
お店の中には素敵なフォルムの薪ストーブたちがいっぱいあるんですが、実際スローライフ、エコロジーとか、考えさせられる機会がたくさんありまして、そういう意識の中からお店に来られる方もたくさんいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、今、多くなってきています。
聞き手
憧れを持っている方も多いと思うんですけれど、実際に自分の家に入れようと思っていざお店に伺うと、大立目さんの役割というのは、どういうところにあるんでしょうか。
|
-
|
ここにあるのは、ストーブ本体だけなんですが、ストーブとして機能するためには、本体、煙突、取り付け、工事、一式で考えます。
新築であれば、図面を見せていただいて、お客様のご希望を聞いて、そこから始めていくんですが、後付け、既存の住宅に取り付ける場合は、必ず呼んでいただいて、見せていただいて、どういう状態であれば、安全で快適に使えるかを打ち合わせしてきます。
|
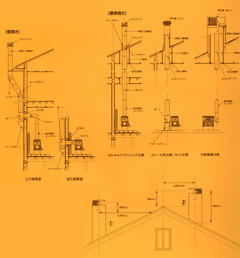 |
|
聞き手
お断りするケースもあるんですか。
あります。
お客様はとってもほしいと言っているんですが、既存の住宅のままだと、どうしても煙突がうまく出せない、煙突を出すことに無理がある。それから、新築であっても、そのお客様の年代や生活の仕方に無理がある場合もあります。なかには薪の調達が難しい方もいます。岩手に住んでいれば、まず大丈夫です。
無理をすると、お客様が後々苦労されることもありますので、あまり無理な場合にはお断りすることもあります。
聞き手
まさに、こう、生活なんですよね。
そうです、岩手の冬は約半年で、たまに使うのではなく、毎日の生活で使う道具のことですから、無理をしないことは大切なことだと思います。
聞き手
煙突のお話をされていましたけれども、これまでの薪ストーブの煙突というとブリキ一枚で、すぐ熱さが伝わってくるようなイメージをされている方もいると思うんですが、煙突が重要なのは、どういうところなんでしょうか。
|
-
|
 Encore
Encore
バーモント
キャスティングス
|
煙突はとても大事です。
ヨーロッパとかの住宅を見るとわかりますが、建物に必ず煙突が付いてます。それは、煙突がストーブを、暖炉を燃やしているんですね。
日本は特殊な事情で、囲炉裏から、すぐ石油ストーブになった国なもんですから、日本で煙突というと、昔の建物それ自体が煙突効果で、建物が煙突の役割をしていたんです。煙りを屋根の煙出しから出す、茅葺き屋根の時代ですね。それは、防虫、防カビ、防風、いろんな意味で有効だったんです、煙りを出すっていうことでは、ヨーロッパのように建物に煙突が入っていて、そこに、きちっと暖炉をつないで、煙突が暖まって上昇気流が起き、きれいに燃やしてあげること、これは日本の住宅ではできなかったことなんです。
昔、囲炉裏だったところに櫓(やぐら)をかけて布団をのっけたのがこたつです。その場所に鉄板のストーブを置いて、煙突をずーっと横に引っ張っていって、軒からちょこっと上げたのが、日本の薪ストーブの使い方だったんです。煙りは確かに外に出たんですが、きちんと燃えなかったので、部屋に煙りも出ましたし、煙突の掃除もたいへんでした。
この煙突というものが、薪ストーブ、暖炉にとって、一番の大事なものなんです。
|
-
|
|
-
|
聞き手
ただ煙りを出すためのものではなくて、煙突が上昇気流を起こす大きな役目となっていたんですね。燃やすところは、薪ストーブ、暖炉の中だけではないようです。
そうです。どちらかというとストーブよりも、煙突がメインといってもおかしくないくらい、煙突さえ良ければ、どういうストーブでもきれいに燃えます。
聞き手
なるほど、そういう意味で、施工が大事になってくる、そこにはいろいろな制約もでてくるということですね。
そうです、私たちの仕事のほとんどの部分は、煙突を如何にうまく付けるかということになります。
聞き手
この薪ストーブなんですけども、今の近代的な石油ストーブの方が火力が強いんじゃないかっていう人も中にはいると思うんですが、薪ストーブのパワーというのは、どの位のものなんでしょうか。
数値、kCal、kWでいうと、さほど大きくないんですが、持続して長ーく熱が出ますから、非常に暖かさを感じます。現在の高気密、高断熱の住宅は、建物が熱を溜める力がありますので、愛称がいいです。また、古いお宅、エアコンでもヒーターでもなかなか暖まらないという住宅でも、薪ストーブは、基本的に輻射熱の暖房器ですから、遠くまで、じわーっと暖まります。とてもあったかい、といつもお客様に言ってもらいます。
聞き手
見た目にも、あったかいですもんね。
|
-
|
 Resolute Acclaim
Resolute Acclaim
バーモント
キャスティングス
|
そうですね、やはり、炎を見るっていうのは、人の気持ちをとても暖かくしますし、楽しいですし、昔の囲炉裏、囲炉裏端もそうでしたが、炎を見ることができるのは他に変えられない魅力があります。
聞き手
茅葺き屋根の時代の住宅の構造から、現在の高気密、高断熱の住宅まで、さまざまな部分で薪ストーブの良い面が出てくるということですね。
そうです。木を目の前で燃やして、その熱を直接もらえるんですけど、これはとても効率のいいことなんです。薪っていうのは、太陽エネルギーなんですね。薪は太陽の光と二酸化炭素と水と土からの養分でできてます。10年くらいで木は、薪として使えるように成長するんです。きちんと手入れをしていれば、自分が生きている間に、何回も薪から恩恵を受けることができます。それだけに、使うことで山も良くなっていくことになると思います。
|
-
|
|
-
|
聞き手
山の木を使うというのは、住宅などの木材として使うことだけではなくて、薪のように使う用途もあって、それを頻繁に使っていくことによって山も元気になる、そのサイクルですね。
そうです。岩手県等は昭和30年代までは、薪炭っていって、一番炭をつくっている時期でしたし、皆さん、自分の地域の山を管理して、計画的に伐採して、植林して、自然萌芽もあり、山といっしょに暮らしていた。そして、大事にしていました。
|
 |
|
-
|
聞き手
薪をつくったり、ストーブのメンテナンスが無理なく楽しめる方は、是非、大立目さんに相談して、炎のあるくらしを考えてみるのもいいんではないでしょうか。
興味のある方に大立目さんからメッセージをお願いします。
なるべく早くお話いただくのが一番だと思います。新築であれば初期段階、基本プラン、間取りをどうしようか、という時期からお話いただければ、一番良い状態で付けることができます。
後付けで、既存の住宅に付けたいという方も、一度、見せてください。そこでお客様のご希望を聞きながら、良い方法を見つけることができると思います。
聞き手
それでは、次は、炎のあるくらしについて、ヨーロッパのノルウェーに行かれた体験も交えながらお話を伺いたいと思います。
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
ホーム
|
(C) IWATE DANRO, LIMITED. All rights reserved.
|

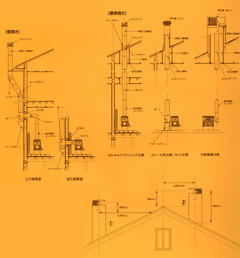
 Encore
Encore Resolute Acclaim
Resolute Acclaim